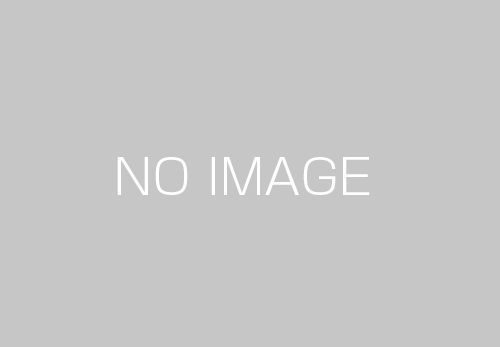前回の(その51)では、『自動思考』について考えてみました。この『自動思考』という考え方が、認知行動療法のコア(核)になる部分ですので、何回かに分けてご一緒に考えてみましょう。前に書きましたが、認知行動療法では、病気の原因としてストレスそのものを考えるのではなくて、ある人がストレスになることを経験した時に、その人が、そのストレスを『心の中で、つまり、脳の中で、言い換えますと、頭の中で、どのように受け取ったか ? 頭の中で、どのように考えたか ? 』、ということが、そのストレスがその人にとって、病気の原因となるようなストレスであったか、病気になるほどの大きなストレスではなかったか、を分けることになると考えるのです。
つまり、そのストレスが、『自分にとっては、大きなストレスである』、と考える人と、反対に、『このストレスは大したことはない。大丈夫だ !! 』、と考えるのを分けてしまう、何かがある、ということになります。認知行動療法では、この何かが、『自動思考である』、というのです。たとえば、今のテーマにしている、『会社で上司にこっぴどく怒られて、この上司は、自分を憎んでいるから、こんなにひどく怒るんだ !! 』、と受け取ったことを考えてみましょう。
この場合に、この怒られた人が、おこられた時に、頭の中で、『怒られたことに対して、脳がどのように反応したか ? 』、ということを『自動思考』として取り上げるのです。それでは少し、この場合の状況設定をしてみましよう。
ます、この上司と部下の関係が、もう何年間も前からの古い関係の場合です。この場合には、上司も部下も、相手の人柄を良く知っていますので、取り組み方は比較的簡単ですね。たとえば、この上司が日ごろはおとなしい温和な人であると仮定してみましょう。その上司が、『相手の部下をこっぴどく叱った』、としますと、この場合には。上司に何か、いつもとは違った何かが働いた、と考えるのが妥当でしょう。たとえば、その日は風邪をひいていて、体調がひどく悪くて、機嫌が悪かった、とか、朝、家を出るまでに、奥さんと大喧嘩をしていて腹が立ったままで会社に来ていた、とかの理由です。この場合には、ひどく怒ったのは一時的な行動ですので、問題はないでしょう。それでは次回からも、もっと考えていきましょう。