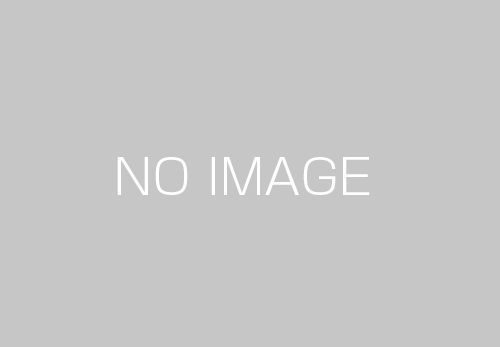前回の(その47)では、睡眠とストレッチの関係を説明しています。睡眠とストレッチの話しが、なぜ、認知行動療法と関係しているのか、という点に皆さまは疑問に思われることでしょう ? 認知行動療法とは、文字通り、認知を問題にする治療法です。ここでいう認知とは、ものごとに対する、『捉え方』のことです。ですので、睡眠が問題であれば、その睡眠という問題について、どのように考えていくか、ということが先ずは始まりとなります。このような、物事についての考え方をどのように進めていくか、ということも認知行動療法の大きな考え方の一つになります。
睡眠障害と言いますと、すぐに、眠ることだけに関心がいってしまいがちですが、このように、睡眠にあまり関係がないように思われる事柄にも注意を向けていく、というやり方が、認知行動療法に取り組む時にはすごく役に立ちますので、今は睡眠についてご一緒に考えています。
さて話しを睡眠とストレッチ体操に戻しましょう。ストレッチ体操をする時には、まずは、ストレッチと睡眠がどういう関係にあったか、を思い出してみましょう。睡眠に入るためには、脳が鎮静化しなくてはなりません。そのためには、脳にいく血流を少なくしなくてはなりません。脳にいく血流を少なくするには、血液を脳ではなくて、身体のほうに行かせればいいわけでは。そのためには、身体の筋肉を緩めてやれば、血液は筋肉に多くいくようになりますので、相対的に脳の血液が少なくなります。そうすれば、脳が鎮静化して、眠りやすくなる、ということになります。
ということで、ストレッチ体操をする時には、身体の中の大きな筋肉から緩めていくのが、睡眠にはとても効果があります。大きな筋肉は、(1)腹筋、(2)背筋、(3)大腿四頭筋(太ももの前側の4つの筋肉)、(4)大腿三頭筋(太腿の裏側の筋肉)です。これらの筋肉を均等に緩めることで、血流が良くなり、それが結果的に良い睡眠をもたらしてくれます。
このように、一つの問題を解決するのに、柔軟な発想ができるのも、認知行動療法をトレーニングしておけば、比較的簡単にできるようになります。それでは、次回からは、本来の認知行動療法のケースを取り上げていきましょう。