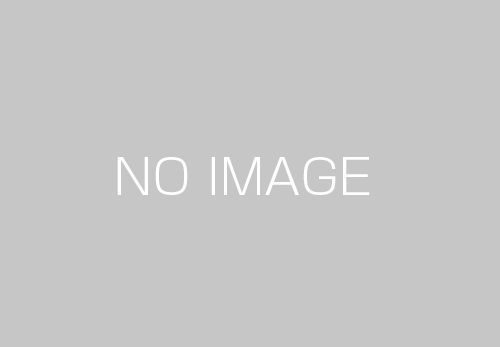前回の(その20)では、睡眠に深い関係がある、寝具などの睡眠環境について考えてみました。今回は、睡眠に関係する『脳内ホルモン』について考えてみましょう。私たちは、夜になれば独りでに眠くなるものだ、と思っています。それは間違いのない生活のリズムですが、もしも、何かの原因で生活のリズムが狂ってしまうと、夜になっても眠られない、ということがおきてきます。
多くの場合の睡眠障害(不眠症)は、そのようなことから始まります。反対に、今日は夜も暑くて寝苦しくて、よく眠れなかったとか、大きな心配ごとがあって、昨日はよく眠れなかった、というような状態は、これは一時的な不眠ですので、心配はありません。それでは、生活リズムが乱れるとなぜ、睡眠しにくくなるのでしょうか ?
その原因はいくつか考えられますが、大きな原因の一つは、睡眠に関係する『脳内ホルモン』の働きが悪くなることでしよう。
睡眠に関係している脳内ホルモンは、いくつかありますが、それらの中でも、睡眠の時間をコントロールしているのは、『メラトニン』という脳内ホルモンだといわれています。このメラトニンの働きで、夜になれば眠たくなり、朝が来れば目が覚めておきる、というリズムが保たれています。しかし、何かの原因でこのメラトニンの分泌が悪くなったり、メラトニンそのものが少なくなってしまうと、夜になっても眠たくならず、睡眠のリズムが狂ってきます。
ではどうすれば、メラトニンがうまく働くようになるのでしょうか ? 皆さまはよくご存知のように、一般的には脳内ホルモンは、大きなストレスなどの心理的な条件に影響を受けますので、ストレスがあった日などは眠りにくくなります。メラトニンを調整するのに一番最初にするべきことは、『朝起きた時には、太陽の光をしっかりと浴びること』です。といっても、太陽の光を直接目に受けるのではなくて、光が入ってくる明るいところで、1時間くらい過ごすということです。そうすると、目から入った光が脳を刺激して、約、14~5時間後にメラトニンが分泌されて、眠りを誘ってくれるようになります。かりに、夜、11時くらいには眠りたいと思う場合には、その14~5時間前の夜の8時か9時ころに明るい光を目に入れるといいのです。
続きは、次回に致しましょう。