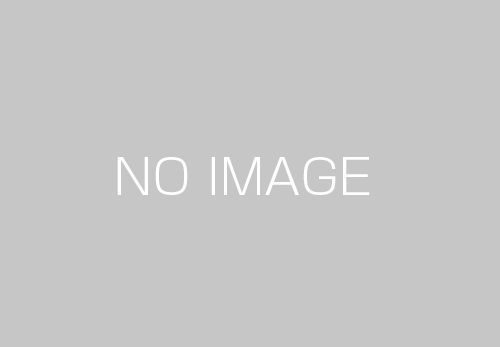前回の(その22)では、あなたのお子さんが、勉強をしないでスマホでゲームばかりしているのて、ストレスがたまる、というお話しでした。
今回は、もうすこし別の例を取り上げてみましょう。
あなたのご主人は、サラリーマンですが、毎日毎日、夜遅くまでお付き合いでお酒を飲んで帰宅します。あなたは、そういうご主人の生活態度に我慢が出来ないので、いつも大きなストレスを抱えています。そして、ある日、とつぜん、堪忍袋の緒が切れて、『あなた、もういい加減にしてちょーーだい。私は、家を出ていきます!!』、というように、爆発してしまいました。
この場合には、認知行動療法的に考えると、どのようになるでしょうか ? まず、あなたの頭の中に、どういうふうな考え方のパターンがあるかをみておきましょう。
あなたの頭の中には、次のような考えがあることでしょう。結婚して家庭があり、子どももいるからには、夫たるもの、独り身の時とは違って、いろいろな責任があるはずだ。のに、毎日毎日、夜遅くまで飲んでいるのは、無責任きわまりない、という思いです。そのために、あなたはいつも、夫に対して不満があります。
そこで、認知行動療法的に考えてみますと、思考パターンの幅を広くすることがまず、重要なことですので、たとえば、『会社に勤めていれば、妻には分からない、いろいろな事情があるだろう。休日には、夫として、家庭サービスもしてくれているので、それで、満足ではないか』、と考えてみます。
または、会社でのお付き合いに出なければ、仕事の効率が悪くなって、うまく勤まらないのではないか。元気に仕事をしてくれているのだから、まあ、良しとしよう』、と考えると、ストレスも少し少なくなりはしませんか ?
このような思考パターンに変化できれば、認知行動療法的な取り組みによって、ストレスはかなり少なくすることが出来ます。
次回は、もう少し、例をあげて考えてみましょう。