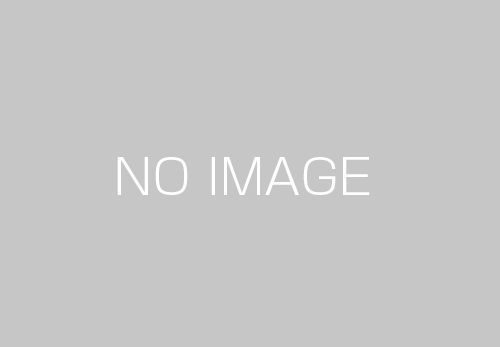前回の(その21)では、ご自分の小学5年生の子どもさんが、毎日毎日、勉強もしないでスマホでゲームばかりしている、ということに不満で腹が立つ、というお話しでした。このような場合に、認知行動療法的に問題を解決しようとしたら、どのように取り組むのでしょうか ?
問題を考える時には、まず、視野を広くして、あらゆる角度から問題を見直してみるのでした。たとえば、(1)『この子にとっては、スマホで遊びほうけることも、これからの長い人生の一場面だから、長い目で見れば、必要な事の一つではないか ? 』、というふうに考えるとどうでしょうか ? または、(2)『スマホでゲームをすることがないと、他の友だちとの話題についていけなくて、仲間外れにされるのではないか ? 』、というふうに考えるとどうでしょうか ? または、(3)『今、しっかりと注意をしておけば、今は聞き入れなくても、ゆくゆくは、自分の判断で、いいことと悪いことを区別できるようになるだろう。その時を期待しよう。』、というふうに考えてみてはいかがでしょうか ?
ようは、子どもは将来、自分の力で生活をしていかなくてはならないわけですので、今は、親として、そのために役に立つことをしておく、という考え方でいるのが一番良いやり方ではないかな、という考え方です。
そういうふうに考えますと、ご自身のストレスがかなり軽減されることに気がつくと思います。そこで、そういうふうに考えた時のストレスレベルを、ご自分で採点してみるのです。
たとえば、認知行動療法的に何も考えないでいた時には、『腹が立ったレベルが、8』だったとします。そして、認知行動療法的に、上の『1』から『3』までを考えたら、『腹が立ったレベルが、5』になったとしたら、『ストレス度が、3、下がった』、という効果があったことになります。
認知行動療法では、こういうふうにトレーニングを積んで行って、ストレスを軽くする練習をするわけです。
次回も、同じように例題を使って考えてみましょう。