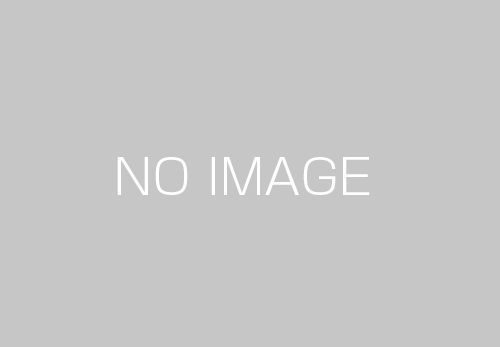前回の(その12)では、物事に出会った時に、まず、どのように考えるかで自分の受け取り方が大きく変わる、というお話しをしました。その一つとして、白か黒かをつけないと、気が済まないという考え方があることをご紹介致しました。
それでは、少し具体的な例をあげて、一つずつ、考えていきましょう。まずは、〖1〗白か黒かつけないと気が済まない、という考え方の場合です。日ごろ生活をしていますと、まあいいか、妥協しておこう、と譲らなければならない場合がよくありますね。
しかし、白か黒かつけないと納得が出来ないタイプの人は、妥協が出来ませんので、〖あくまでも、白か黒か、これかそれか、あっちかこっちか、をはっきりしてくれ!!〗、と求めます。
しかし、人それぞれに考え方が違いますので、そのような自分の考え方は、受け入れられない場合が、とても多いので、結局はそういうタイプの人は、精神的にも、心理的にも非常に疲れて、自分にとっての大きなストレスになります。
認知行動療法では、そういう時には、どのように対応するか、ということをドリルワーク形式で練習していきます。結果として、精神的にすごくラクに対処できるようになるのを目標としています。
たとえば、友人と旅行の計画を立てる時に、一人は北海道へ行きたいと言い、もう一人は、九州へ行きたいと言ったとします。自分は、北海島に行きたい希望ですので、あくまでも、北海道に行こうと主張しますが、大勢が九州行きの希望ですので、結局、イヤイヤ、シブシブ、ついていくことになり、折角の楽しいはずの旅行が楽しくなくて、それどころか、『こんな旅行なら、高いお金を払ってまで、来なければ良かった』、と思うことになります。
これでは、何のための旅行かがわからなくなり、大きなストレスになってしまいます。それではどのようにすればよかったのかについて、次回に考えてみましょう。