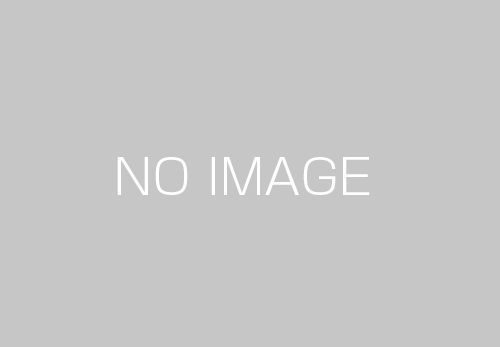前回の(その9)では、人は『○○すべきである』、というように、一つの決まった考え方のパターンを持っていることが多い、ということをご説明しました。
それでは、そのような考え方には、どのようなパターンがあるのでしょうか ? 認知行動療法を開発したアメリカの精神科医のアーロン・ベックは、それにはだいたい、10種類くらいのパターンがあり、それを知ることによって、その人の考え方の全体を推測できる、としています。
つまり、その人その人のいくつかの考え方は、だいたい、その人によって決まっていて、そんなにたくさんあるものではなくて、せいぜい、数種類に限られるので、その人は、それらの自分の考え方のくせを、トレーニングによって修正していけば、ほとんどの場合に適応ができる、と主張しました。
たとえば、今話題にしている、『ご主人に台所の後片付けを頼んだ奥さん』について考えてみましょう。
この奥さんが、『ご主人に台所の後片付けを頼んで、一家の主人であるからには、妻が忙しい時には、台所の後片付けくらい、するべきである』、と考えましたが、この奥さんが、たとえば、自分の子供たちが、勉強もしないで、スマホばかりしていたと仮定しましょう。
それを見た奥さんは、たぶん、『子供はスマホなんかしてないで、勉強を、するべきでしょう!!』、と思って、子供たちを叱ることは容易に想像できます。
結局は、この奥さんの判断基準は、『人は人それぞれの立場に置かれた義務を果たすべきである』、という考えが、真っ先に浮かんできますので、それに反した行為を許さないことになります。
このような考え方が、自分の感情を自分で害してしまい、大きなストレスになることが想定されるのです。