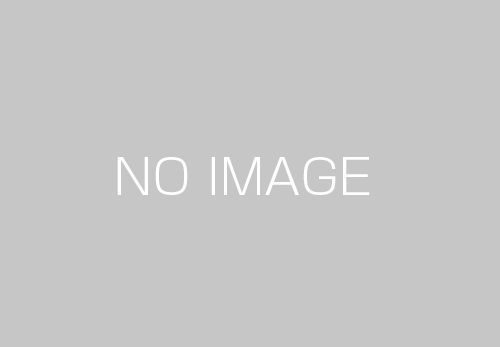前回の(その35)では、『諸行無常』の意味について考えてみました。諸行無常は、意味の取り方によっては、大きなストレスになる場合もありますし、反対に、そんなに大きなストレスにはならず、却っていいストレスになることもあります。今回は、良く知られている例をあげて、考えてみましょう。
第二次世界大戦の時に、ナチスドイツがユダヤ人を大量に「強制収容所」に収容して、大量虐殺をしたことは皆さまもよくご存知の通りです。その時に、ヴィクトール・フランクルというオーストリア人のユダヤ人がいて、この人が収容所に収容されました。フランクルは、優秀な精神科医でした。彼の妻と両親なども収容されて、収容所内で亡くなりました。フランクルは精神科医でしたから、収容所に入っている間に、同じように収容されている人々の行動と精神的な状況をことこまかく観察していました。そしてその内容を、隠し持っていた小さな紙切れに詳細に記録していたのです。その記録をもとに、収容所から解放された1945年の翌年に、『(邦題)夜と霧』という本で出版しました。その本によりますと、彼の詳細な観察の内容がよく分かります。ある年の年末に、クリスマスが近づいてきていた頃、収容所内であるうわさが流れたそうです。そのうわさの内容は、『今年のクリスマスには、イヴの日に、収容されている者が解放される』、という内容だったそうです。
そして、フランクルが観察したその経過がこまかく書かれています。同じ収容されている人々の中でも、クリスマスが終わってから、極端に衰弱して死亡した者もあれば、比較的元気で過ごしていた者もいたそうです。フランクルは、なぜこのような差が生まれたのかについて、精神科医として考察し分析をしました。その結果、このうわさを信じて、解放を心待ちにしていた者は、クリスマスのあとでのストレスが大きく、衰弱が激しかったということです。反対に、うわさを信じないで、平静でいられた者は、クリスマス後のストレスが小さくて済み、元気でいられたということです。
つまり、自分が期待していたことが裏切られた失望感がストレスとなり、その人の健康を大きく左右した、ということになります。いつも気持ちを柔軟にもって、環境や状況にしなやかに耐えられるようにしておくことは、ストレスコントロールという点からも、私たちの健康にとっても大切なことだということが分かります。次回ももう少しこのことを考えてみましょう。