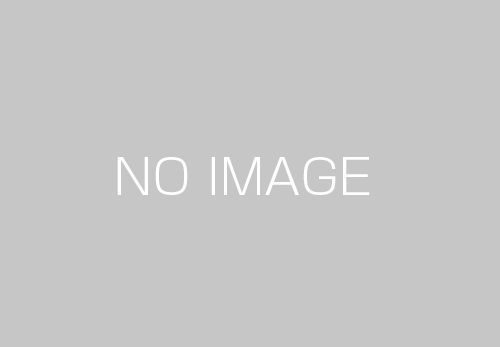前回の(その21)では、睡眠を誘う脳内ホルモンである、メラトニンについてご紹介しました。メラトニンは、目から光を入れてから、14~15時間すると、脳内でメラトニンが分泌されやすくなりますので、眠りに入りやすくなります。
それでは次には、このメラトニンを脳内で作り出すには、どうしたらいいのかを考えてみましょう。メラトニンは物質ですので、その原料となるものは、当然、食べ物から摂取されます。そのために必要な食べ物は大体わかっていて、『トリプトファン』という必須アミノ酸です。ご存知のように、必須アミノ酸は、体内では産生できませんので、食べ物から摂取しますが、トリプトファンが多く含まれているのは、タンパク質が豊富な、卵や大豆などです。意外に思われますのは、お蕎麦がトリプトファンの含有量が多いことが知られています。
このトリプトファンを摂取しますと、まずは、『セロトニン』という脳内ホルモンに変化します。ご存知のように、セロトニンは気分の変化を調整したり、やる気に影響をしたりする大事な脳内ホルモンの一つです。このセロトニンがメラトニンに変化することで、夜になると眠たくなってくる作用があります。このことから、セロトニンが不足したりして、たとえば、うつ状態になりますと、睡眠も悪くなる可能性がありますので、逆に考えますと、睡眠の状態がいつもと変わるということで、精神的なうつ的な状態が推測できることになります。
いずれにしまして、睡眠状態は、私たちの健康状態を調べるのには、とても、大きな参考になります。
では次回もメラトニンなどの脳内ホルモンについて、もう少し考えていきましょう。