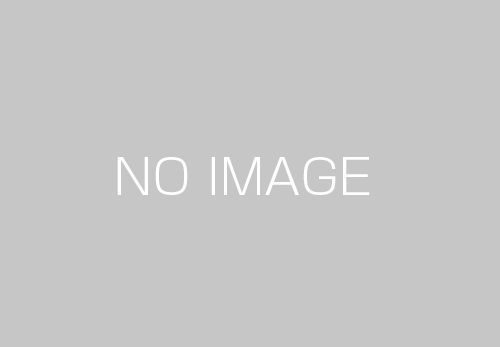前回の(その38)では、傾聴型のカウンセリングでは、心理的な悩みは少しは解消されますが、身体的な症状は解決されることはなかなか難しいということがあると説明しました。その理由は、心理的な要素が、身体面に現れるには、時間がかかり過ぎる、という点にあります。傾聴型のカウンセリングは、あくまでも、心理的な面でのリラックスを目的にしていますので、身体的な症状には、別の手法を実践する必要があります。
そこで、たとえば、認知行動療法を適用することを考えてみましょう。もしも、相談者が、夜よく眠れない、という症状を訴えたとしたら、まずは、睡眠を良くすることを考えなくてはなりません。相談者が、カウンセラーに相談しに来るということは、カウンセラーが何か、自分の症状をよくする方法を適用してくれるに違いない、と期待しているわけですので、まずは、その期待に応えないことには、相談者とカウンセラーとの間の、『信頼関係』は築くことができません。この信頼関係のことを、『ラポール』とよんでいます。カウンセリングでは良く聞く言葉ですので、覚えておくと役に立ちます。
睡眠を良くするための認知行動療法は、非常によく使われる手法です。まず、睡眠が悪い日が続きますと、誰でも、今夜もまた、よく眠れないのではないか、と心配になります。そうすると、その心配な気持ちがさらに、眠りにくい気持ちを強くしてしまいます。つまり、眠れない⇒心配だ⇒眠れない・・・、という、悪循環に陥るわけです。そうなってきますと、自分ではなかなかこの悪循環を断ち切ることが出来なくなってしまいます。
そこで、認知行動療法では、『眠れないことが心配だけれど、実際に眠れないと、どんな不都合が起こるのか ? 』、と自分自身に問いかけて、その不都合なことに関して、自分の考えをまとめて見る、というやり方をします。
それでは、次回では、もう少し具体的なやり方を進めてみましょう。