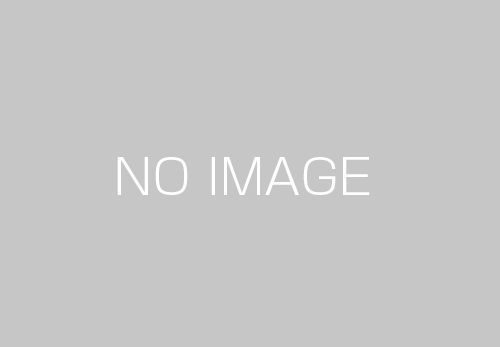前回の(その37)では、傾聴型カウンセリングと認知行動療法との併用の利点をご紹介致しました。傾聴型のカウンセリングは、現今では主流のやり方ですが、実際にこのカウンセリングを受けて、充分に納得できて、しかも、効果が出る場合は少ないと言わざるを得ません。その理由は、カウンセリングを受ける人は、心理的な悩みだけを持っている場合が少ないということにあります。
以前から、ストレスは心の面と身体の面の両方に現れることが多い、とご説明しました。傾聴型のカウンセリングは、文字通り、心の面への効果は期待できますが、身体の面への効果は期待ができません。
そうかと言いましても、傾聴型のカウンセリングと認知行動療法を併用しても、身体の症状を改善することも、これもまた、難しいことになります。このような場合には、身体心理学的なやり方たが効果が期待できるのですが、このことはおいおいご紹介していきましょう。
さて、本題にもどって、傾聴型のカウンセリングの進め方をみてみましょう。このカウンセリングを受ける時には、たとえば、相談者が仕事の悩みをもっていて、最近、忙しくて、夜、よく眠れないと仮定します。そして、カウンセラーに、『最近、残業が多くて帰宅が遅くなり、夜もゆっくり眠れません』、と訴えたとします。そうするとカウンセラーは、『○○さん、そうですか、仕事が忙しくて夜もゆっくりと眠れないんですね。つらいですね。』、と応じます。このようなやり方は、こころの気分転換にはなりますが、このカウンセリングで夜よく眠れるようになるわけではありませんし、仕事の悩みが解決されるわけでもありません。結局は、相談に行った人は、何も得るものがなく時間とお金だけを使うということになります。
こういう現実が実際には繰り返されているのです。それでは、認知行動療法を使った場合には、どのようなやりかだになるかを次回では考えてみましょう。