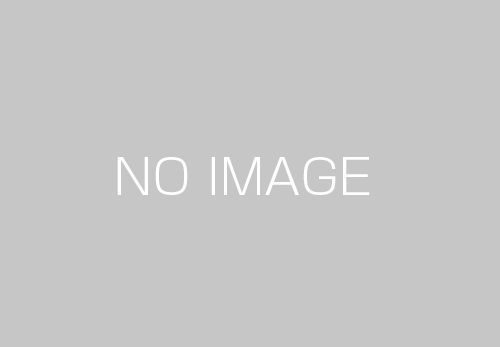前回の(その36)では、認知行動療法を受ける場合には、カウンセラーに相談することになります。カウンセラーに相談する時には、どのようにしてカウンセラーを選んだらいいのか、ということについて話題にしました。皆さまは、カウンセラーに相談したいと思っ時には、どんなことを期待してカウンセラーに会おうとしますか ?
たぶん,多くの方々は、『カウンセラーさんに相談すれば、今の問題を解決するために、何か、いいアドバイスなり、いい助言をしてくれるだろう』、という気持ちで相談されると思います。しかしながら、現今のカウンセラーは、カウンセリングをするにあたって、『相手の人に、助言をしたり、アドバイスをしてあげよう』などとは、全く考えていないのです。それは、長いカウンセリングの歴史の中から、『○○さん、こういうふうにしたらどうですか ? 』、というような指導をすることのマイナス面が問題になってきたからです。つまり、相談する人が、カウンセラーに、『依存する』という構図になってしまうからです。そうすると、結果は期待したとはうらはらに、効果が出にくくなり、それどころか反対に、マイナスの面が出て来てしまうのです。
認知行動療法を指導しているカウンセラーが少ないという現実も見逃せません。カウンセリングを受ける人は、どちらかといえば、自分ではものごとを決められないというタイプの人が多くおられます。そういう人に対して、『このようにしたらどうですか ? 』、と投げかけるのは、プラスにはならないで、逆にマイナス面が多いというわけです。ではどうするかということになりますと、カウンセラーは、『相談に来た人の話しを、ただ、ひたすらに聴く!!』という態度で臨みます。このような取り組み方を、『傾聴型カウンセリング』と言います。最近のやり方は多くの場合にはこの方法ですが、しかしはたして、効果が現れるかと言えば、思うような効果が現れない場合も多いのです。そこのところを、相談に行く人は、前もって考えておかなくてはなりません。認知行動療法と傾聴型カウンセリングと、併せて指導してくれるカウンセラーを選ぶということになります。
次回ももう少し、この問題を考えてみましょう。