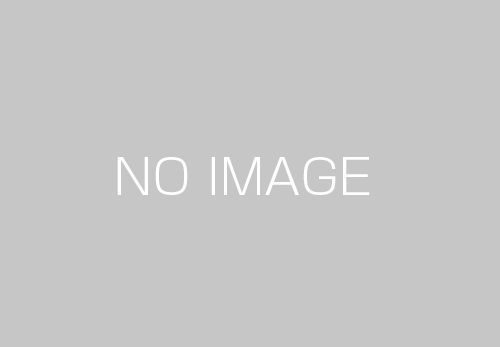前回(その23)に続いて、今回も日ごろよくありそうなケースについて、考えてみましょう。
例として、あなたがサラリーマンで、ある会社に勤めていると仮定しましょう。ある時、人事異動があって、あなたは今まで全く知らなかった部署に異動したとします。
部署の人たちとも今まで面識がなく、その上に、仕事の内容も、前の職場とはぜんぜん違います。異動した最初の日に、皆さんは忙しそうに働いています。職場の上司から、新しい仕事の内容について説明を受けましたが、頭ではわかっていても、いざ、実際に仕事にとりかかろうとすると、何から始めていいものやら、見当もつきません。
そこであなたは、『自分は、新しい職場では何をしていいかもわからない、能力のない人間だ!!』、と落ち込むこともあるでしょう。あるいは、『新しい上司は、もうちょっと、詳しく分かりやすく、新しい仕事の内容を説明してくれればいいのに!!』、と腹立たしく思うかもしれません。はたまた、『職場でのこのくらいの変化についていけないのでは、これからのサラリーマン人生はうまくいくのだろうか ? 』、と悲観的になるかもしれません。あるいは、そのまったく逆に、『今は何もわからなくて、仕事がうまくできないけれど、そのうちに何とかなるだろう ? 』、と楽観的に考えるかもしれません。
認知行動療法では、このように、ある出来事に出会った時に、自分がどのような考え方をするかを分析するのが、大きなポイントになります。そして、面白いことには、そういう出来事に出会った時に、人によって、だいたいの考え方の傾向が決っている、ということが分かっています。
そして、『何とかなるだろう』、と楽観的に物事を受け止める人には、大きなストレスは感じられませんので、そのまま新しい職場に適応できていく、というわけです。問題は、そのほかの考え方をする人です。これらの人たちは、おうおうにして、悲観的に、後ろ向きに物事を受け止めますので、強いストレスを感じることになり、健康上のトラブルを生むことになります。
それでは、次回も、上のケースについて、もう少し考えてみましょう。