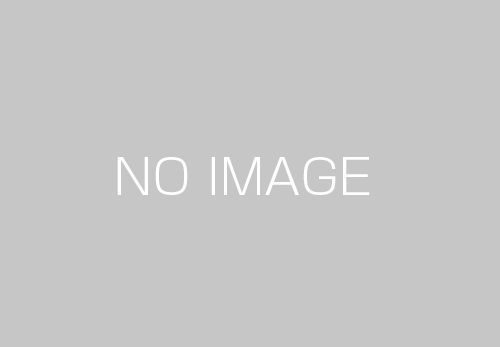前回の(その11)では、『○○であるべきだ』、とか、『○○するべきである』、という『思考パターン=考え方』が、自分の気持ちを縛ってしまい、それに反した現実に出会った時には、大きな心理的なストレスになる、というお話しをしました。
それでは、そういう風に、自分をガンジガラメに縛ってしまうような考え方のパターンには、他にはどのようなものがあるかを考えてみましょう。このことについては、認知行動療法を開発した、アメリカの精神科医のアーロン・ベツクが、詳しく分析しています。そして、その考え方のパターンを知ることによって、それを修正すれば、自分へのストレスが軽減されると考えたわけです。これが認知行動療法のやり方の根幹の一つになっています。
たとえば、前回書きましたが、〖1〗白か黒かをはっきりしないことには納得できない。いわゆる、中途半端なこと、グレーゾーンを認めないという考え方です。〖2〗ある一つのことが起こった時に、そのことが、物事のすべてを表しているかのように受け取ってしまう。つまり、一事が万事と考えてしまう考え方です。〖3〗一つのことが起こった時に、それを全部、自分に起こるに違いない、と自分に関連付けてしまう考え方をする。〖4〗何かが起こった時に、何の根拠もないのに、自分が考えていることとまったく同じに違いない、と思い込んでしまう。〖5〗普通に考えればなんでもないような些細なことを、すごく大げさにとらえたり、逆に、どうでもいいような些細な事のようにとらえてしまう。などがあります。
それでは、次回からは、これらの〖1〗~〖5〗について、具体的な例を挙げながらみていきましょう。